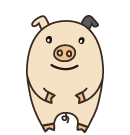小さな国語塾のつぶやき
名歌は起承転結に
漢詩というものは字数、行数が決まっておりしかも起承転結になっていることは中学校で習う。まず一句でテーマを起こす、第二句でそれを承(う)け、第三句で一転する。そして第四句で全体を結んでまとめる。この構成を意識しながら文章を書くように指導されることも多いだろう。さて、国民的名歌は普段は一番だけ歌うということが多いので分かりにくいが、定型詩、しかも起承転結になっている場合が多い。例えば滝廉太郎の「荒城の月」。一番は「春 高楼の」と昔の春、二番は「秋 陣営の」と昔の秋というようにセット提示し三番は「いま 荒城の」と変わって現在の荒れ果てた姿。そして四番は「天上 影は変わらねど」と古今貫いて変わらない自然の姿をまとめている。また北原白秋作詞の「あめふり」、そう例の「あめあめふれふれ母さんが~♪」も見事な起承転結になっている。こういう発見をすると「おおっ」と思わずガッツポーズをしたくなるのである…ぜひ皆さんも昔の歌をたまには懐かしく思い出してみてはいかがか
2014/12/05 11:11
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です