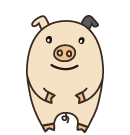小さな国語塾のつぶやき
「花」=「梅」「桜」
「イモ」といえば北海道では誰もが「ジャガイモ」のことを連想するが九州、特に鹿児島では「イモ」=「サツマイモ」なのだ。九州に限らず関東辺りまではおそらく「イモ」=「サツマイモ」と連想するだろう。さて、西洋で「花」といえば「バラ」。ギリシャ・ローマ神話にはバラが登場し、古代ローマでは、「美」と「愛」がバラの属性となった。まさにヴィーナスのシンボルだったわけだが、中世ヨーロッパでは「聖」が属性となり、聖母マリアのシンボルへと変わった。では、日本ではどうかというと奈良時代までは「花」といえば「梅」、平安時代後期以降は「桜」をさすようになった。この歌から「花」は「梅」ではなく「桜」という区切りはないが、遣唐使の廃止以降は中国渡来の梅から、日本特有の花である桜へと感心が高まっていったと考えられる。何が言いたいかというと、時代、地域によってある言葉が特定の意味をもつということ。とくに和歌においては「花」=「梅」か「桜」ということを念頭に置いておきたい。
2014/10/24 11:12
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です